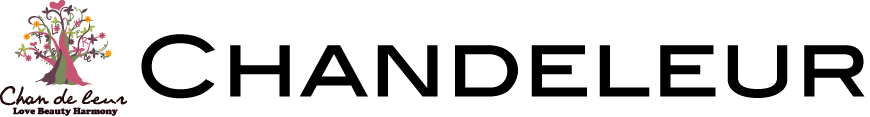幸せのレシピ
日本を出発する直前、荷造りをしていたときに、タッパーに詰めてスーツケースの底に入れた梅干しは、生前の母が作ったものだった。
姉と私は、子供の頃からずっと、この味に親しんできた。
緊張するとお腹が緩くなる性分だった私に、これを食べたら大丈夫やから、と母は、大きな梅干しを箸でつまんで、口の前に差し出した。
あーんと口を開けると、ぽいと放り込まれる。
体をきゅうっと縮めて、すっぱ!と叫ぶ。
その様子を見て、母は、気持ちよく笑っていた。
大人になって、東京でひとり暮らしをするようになってからも、毎夏、母から梅干しの宅急便が届いた。
大きな瓶にぎっしり詰め込まれた、ふっくらとやわらかな梅干し。
ひと粒ひと粒、食べるたびに、母を思い出した。
旅に出るときも、タッパーに入れて、必ず持参した。
どんな僻地へ出かけても胃腸をこわさなかったのは、この梅干しのおかげだったと思う。*1
どこかへ旅行をする時に「必ず持っていかなければならない物」は人によってさまざまです。
私にとっての必需品はフラワーエッセンスとホメオパシーです。
せっかくの旅行だから、「安心して、楽しく、快適に」過ごしたいからです。
娘は修学旅行に数字やアルファベットの風船を持って行っていました。
ホテルの部屋をデコレーションして友達と写真を撮るのだと。
四泊五日の旅行で、ただでさえ荷物が多いのだから風船はいらないのではないかと私が言うと、それほどかさばる物ではないし、他のものを諦めてでもこれは持っていくと話していました。
「お母さんの手作りの梅干し」も「フラワーエッセンスとホメオパシー」も「数字とアルファベットの風船」も、他の人から見れば「それいる!?」と思えるものであっても、本人にとってみれば必要不可欠なのです。
たとえば人の人生をひとつの「旅」と考えるとして。
私たちはさまざまな考え方や生き方、価値観などを「あれも必要、これも必要」とスーツケースに詰め込みながら成長していきます。
そしてそれらの多くは、子供の頃に一番近くにいて育ててくれた(多くの場合は)お母さんの影響を色濃く受けています。
この世に完璧な人など存在せず、それはお母さんだって例外ではありません。
お母さんは不得意なことや欠点を抱えながらも、ひとりの人間をゼロから育て上げなくてはいけないのです。
本当にこれで正しいのだろうか
自分の子育てに対して100%の確信は持てないし、良かれと思ってしたことが逆効果だったこともある
それでも子育ての根底にある想いはいつも同じです。
どうかこの子が幸せな人生を歩めますように
たくさんの自問自答と試行錯誤を繰り返しながら、お母さんは自分なりの子育てのレシピを作り上げていきます。
このレシピに詰め込んだ沢山のものが、わが子の幸せのレシピとなることを願いながら。
「瀬々はわたしじゃないし、わたしの所有物でもない。
生まれた瞬間から道は違っていて、今は太い一本に見えてるけど、ちゃんと枝分かれしてるんだよ。
だんだん距離が開いて、手もつなげなくなる日がくる。
それまで、瀬々の行く先にある障害物や穴をできるだけ処理してあげたいけど、ひとつ残らずは無理だし、道を決めたり、代わりに開拓したりなんてありえない」
だからあなたも自由に生きていいと思う *3
お母さんは自分が持っているすべてを伝えたら、その後は子供たちが必要なものだけを選んでいいと思います。
親と子供は違う人間なのだから、何を選択して、何を必要不可欠とするのかも違って当然のことです。
せっかく大人になったのに正しいほうを、幸せなほうを選べないなんて、選ばないなんて、そんなことがあるの? *3

北海道で作られたくるみフラワーエッセンスは人生に起こるさまざまな変化に順応できるように助けてくれるエッセンスです。
くるみは硬い殻を突き破って芽を出し、いずれ大木へと成長します。
お母さんは「考え方」や「生き方」や「価値観」など、沢山の「可能性の実」を子供たちに贈ります。
それらの中には子供たちを雨風から守ってくれる大木へと成長するものもあるでしょう。
けれども贈られたすべての実が芽を出す必要はありません。
すべてを両手に抱えて、身動きが取れなくなってしまうよりも、自分にとって必要なものだけを選んで大切に育てることが、お母さんの想いを理解して受け取ることに繋がるのではないかと思います。

硬い殻で身を守っているくるみの姿のように、周りの影響から私たちを守り、変化の波に乗れるよう助けてくれます。
過去のしがらみや他人からの影響で変わりたいのに変われないと囚われてしまった心を解放して、新しく変わる方向へと舵を切ることをサポートします。
引用:
*1 2017年 株式会社講談社 原田マハ
『あなたは、誰かの大切な人』ページ93/163
*2 2022年 株式会社文藝春秋 一穂ミチ
『光のとこにいてね』ページ308/424
*3 2022年 株式会社文藝春秋 一穂ミチ
『光のとこにいてね』ページ134/424