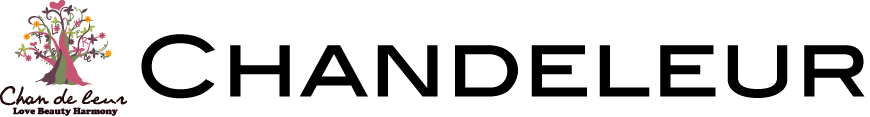世界はまだまだ面白い
光のなかから生まれてきました
きよらかな天の高みから
この地上に降りてきました
大地でしっかり生きるため *1
2025年が幕を閉じる。
はぁ、しんどい。
うっかり気を抜くと、心の中でそう呟いてしまう一年だった。
もちろん、良いことや嬉しいこと、息が苦しくなるくらい大笑いした日もあった。
だけど、もともと内向的な性格が、さらに内へ内へと閉ざしていく。
だって、どうすることもできないじゃん。
何度も心の中で、だれともなしに言い訳をした。
本当はどうにもできなかったわけじゃない。
動かないと決め、『停滞』を選び続けたのは紛れもなく私だ。
もし、今の状況がこの先ずっと続くとしたら、あなたから引き出されるべき資質とは何でしょうか。
マイケル・バーナード・ベックウィズ
状況が変わるのを待つのではなく、私にできることは……
だめをだいじょうぶにしていく日々だよ *2
たとえば、ついムッとしてしまう幼さとか、臆病なところとか、弱いふりをする卑怯さとか。
「だから私はダメなんだ」とこれまで、ただバッテンをつけてきたこと。
それらの欠点を『だいじょうぶ』なものに変えていく努力を積み重ねること。
喜怒哀楽。
『喜』と『楽』は良いもの。
『怒』と『哀』は悪いもの。
これまでずっとそう仕分けをしてきたけど、『どんな気持ちも価値があるもの*3』で人生に夢中になれるヒントを与えてくれている。
だから、沸き起こるどんな気持ちにも、どんな考えにも優劣をつけたり、頭ごなしに否定したりせず、ただ静かに受け入れてみる。
ジャーナリングを通して、ひたすら心の中の自分と対話する。
そうやって、悩みの根っこにあるものに気づいていく作業は地味で時間がかかるものだけど、そこまで本気で、自分の人生のために行動してあげられるのは自分自身しかいないだろう。
心理学者のダニエル・カーネマンらによって提唱されたピーク・エンドの法則。
わたしたちは、ある出来事について全体的にどうだったかを判断するとき、その時間の長さはほとんど無視し、感情が最も高まった瞬間(ピーク)と、その出来事がどのように終わったか(エンド)、この2点だけで記憶を評価するという。
私たちの脳は、経験したすべての瞬間を平等に記録するわけではなく、印象的な場面だけを拾い上げ、それをつなぎ合わせてひとつの物語をして保存するそうだ。
だとしたら、2025年というこの年をどのように終わるかが、とても重要になのではないか。
喜んだこと。悲しかったこと。怒ったこと。絶望したこと。困惑したこと。勇気を出してやってみたこと。面倒くさいとごねる自分をなだめながら頑張ってみたこと。
それらのすべてをノートに書き連ねる。
そしてどのページにも赤ペンで大きな花まるをつけていく。
『世界はまだまだ面白い』
ショッピングモールの入り口に貼られていたポスターのキャッチコピーが目に留まる。
流れは、いつでも自分で作り直すことができる。
まだまだこれから。
面白い世界を、私が私のために作っていこう。
今年も一年、ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
もうダメかもしれないと落ち込みながらも、それでも…と希望を取り戻したい時に私が手にするエッセンスたちです。

大切な人や物、必要としている状況などとのご縁を引き寄せます。
まさに、潜在意識を活用して、目の前の現実を変えるのに、最もぴったりなエッセンスです。*4

明るく前向きで楽観的な気持ちになれるフラワーエッセンスです。
このフラワーエッセンスをとると、まるで魂がワルツを踊るように気持ちが弾み、笑顔で毎日を送れるようにサポートをしてくれます。*5

パートナーシップや経済的な問題を解決するサポートをしてくれます。

ボグブルーベリー(アラスカンエッセンス)
人それぞれの「豊かさ」に繋がることを助けてくれます。
頭で考えるかハートで感じるかを通して、自分自身が深いところで欲している「豊かさ」につながりやすく助けてくれます。*6

ピンクプリムローズ(ロータスウェイ)
恐怖、ためらい、躊躇を解き放ち、人生や仕事での大きな変化への適応を助け、行き詰りや停滞を素早く乗り越えるサポートをします。
引用:
*1 2023年 twililight きくちゆみこ
『だめをだいじょうぶにしていく日々だよ』12ページ
*2 2023年 twililight きくちゆみこ
『だめをだいじょうぶにしていく日々だよ』6ページ
*3 2025年 株式会社河出書房新社 吉川めい
『本心に気づき、自分を生きる 書く瞑想ノート』100ページ
*4 2022年 株式会社彩流社 YOKOKO
『「花の波動」で幸せな人生を手に入れる』181ページ
*5 2022年 株式会社彩流社 YOKOKO
『「花の波動」で幸せな人生を手に入れる』175ページ
*6 2021年 ネイチャーワールド株式会社
『大自然からの贈り物 こころと体を癒す世界のフラワーエッセンス』272ページ